七人の日常(一)・
-金坂亮子編『お父さんが亡くなった桜の木の下で……』-
-金坂亮子編『お父さんが亡くなった桜の木の下で……』-
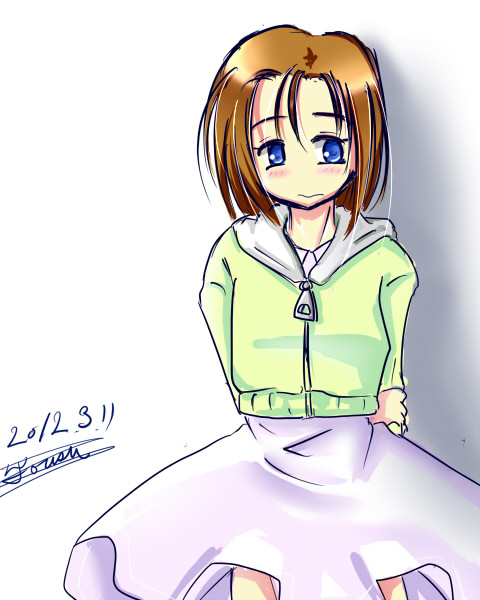
名前:金坂 亮子(かねさか りょうこ)
誕生日:7月6日
身長・スタイル:153cm 細くて華奢な体型。胸は殆ど膨らんでいない
好きな食べ物:アップルパイ。りんごが好き
苦手な食べ物:わさび。ツーンとくるのがダメだとか
好みの男性のタイプ:自分を見守ってくれる人、大切に扱ってくれる人。……少なくとも、犯したり乱暴にしたりしない人
趣味:折り紙。トランプ。一人で遊べるから
家族構成:両親と死別し、遠い親戚に預けられているけれど、あまり大切にされていない
性格: 大人しい子。幼い頃から義理の兄に虐げられてきて、色々と諦めてしまっている。
ささやかな幸せを望んでは打ち砕かれて傷ついて、ますます内向的になっていく
「……」
桜の花びらが粉雪のようにふわりと舞い落ちる中、亮子は無言のまま佇んでいた。これから自分の身に降りかかるであろう痛々しい出来事を想像するだけで、無駄口を開く気になどなれはしない。まだ幼く、瑞々しい頬をほのかに赤らめて、小さな溜息と共に眉を僅かに寄せ、目を伏せているしかない。
春先の、刺すような寒さを感じる風が亮子の肩を撫でている。亮子はこれから衣服を自ら脱ぐよう強要されるか、あるいは男の手によって強引に脱がされ、無防備な肌を晒すことになるのだった。この、どんよりと曇った寒空の下で。
「おい。何黙ってんだよ」
「ご、ごめんなさい」
いつのことだったか、一方的に決められたルールがあった。それは『二人きりの時は敬語を使え』ということ。そのルールを決めた男の鋭い目線が、ぎろりと亮子を突き刺していく。亮子はただ恐怖に脅えるだけ。もはやどうあがこうが無駄だとわかりきっているのに、耐えることなどできはしないのに、体の震えはどうしても止まらない。
(お兄ちゃん。……なのに)
――亮子は数年前に両親を亡くし、天涯孤独の身になっていた。そうして紆余曲折がありながらも結局、遠い親戚の家に引き取られることになったのだ。が、あまり愛情を注がれてはいなかった。それだけならまだしも、同居することになった不良男によって、日々性的な営みを強要されているのだった。亮子にとっては兄のような存在だというのに、物を扱うかの如く酷い事をされてきた。それも、数え切れない程。
そうして今日もまた、男は無慈悲な要求を突き付けてくる。例えば、いつだったか男は戯れに言ったものだ。『おい。お前の親父がぶっ倒れた場所でヤろうぜ』と。亮子のトラウマをあえて刺激するようかのように非常識な提案を平然としたものだ。わざわざそんなところに連れて来られて犯されて、弱々しく泣きじゃくっている亮子を見下ろして、男はますます興奮したのか、更に何度もしつこいくらいに亮子の膣内奥深くまで一物を突き立てたのだ。それ以来この桜の木の下は、悪い意味での定番の場所となってしまった。
――亮子は尚も無言のまま、僅か目を伏せている。亮子の父は、仕事帰りにたまたま通りかかったこの桜の木の下で倒れてしまった。すぐに発見されて病院へと運ばれたものの、意識を取り戻すことは二度となかった。原因は過労という、至極ありふれたものだった。もし仮に一命を取り留めることができていたら、亮子の未来は大幅に修正されていたことだろう。少なくとも、こんな酷い目に遭うこともなかったはずだ。
「おい、早くしろ」
「……はい。う、う」
亮子は男の要求に応じるしかなかった。新たな要求とは、白い清楚なスカートを掴んでたくし上げ、裾の先端を口で咥えていろとのことだった。亮子は既にショーツを剥ぎ取られてしまっていて、スカートの布地が上がっていくのと同時に、ヘアすら生えていない割れ目が晒されてしまう。その割れ目からは、大量の愛液が分泌されていた。無論、手で覆い隠すことも許されてはいない。そんな事をしようものなら、間違いなく怒鳴られることだろう。慰み者にされた少女はただ痴態を晒し、羞恥に耐え続けることしかできないのだ。
「う……うぅぅぅ。ぐす……。う、う……」
当たり前だけど、あまりの恥ずかしさに亮子は唇を噛みしめる。どうしてこんなことをしなければいけないのだろう? 悔しい思いしか込み上げてこないのに、こんなにも股間を濡らしてしまうように仕込まれてしまったのが、たまらなく悲しい。
「何泣いてんだよ」
また今日も、この男の好きなように陵辱される。体中をべたべたと無造作に触られて裸にさせられる。散々キスをされたり顔中をなめ回された後で、太く長い男性器を喉の方にまでねじ込まれる。剥き出しにさせられたお尻の穴にも、怒張したものを散々突き立てられる。射精する場所は常に気まぐれで、膣内だったり顔面だったり、全部飲み干すよう命令されることも度々あった。そうして仕上げとばかりに最後には霰も無い姿のまま縛り上げられたりされて、晒し者にされる。今日もまたそんな未来が待ち受けている。
「ひっく。うっく……。い、や……」
亮子の頬をぽろぽろと涙が流れ落ちる。そんな中、男の指が亮子の狭い割れ目を引き裂き始めていった。涙如きで心が動くような男ではないのだ。
「嫌じゃねえだろ」
「ひぅっ! や、やああ……。こんな……」
苦痛はまるで無く、むしろ心地良く感じる。だからこそ心が苦しい。そんな体に、いつしか気付かぬうちに変えられてしまったのだから。
「あ、あ、あ……。ううっ……えううぅ〜〜〜っ!」
今日もまた体を玩具にされていく。がくがくと揺さぶられ、軽々と持ち上げられ、顔面に肉棒をぴたぴたと押し当てられていく。恋人同士や夫婦がするものとはまるで違う。愛情など一切こもっていない、一方的に欲望を満たすだけの交わりが始まる。亮子は単なる性欲の処理に使用されていく。これではまるで文字通り、トイレ代わりだと亮子は思う。
「い、いやあぁ! ご、ごめんなさい……ごめんなさいいぃぃ! やめてえぇぇ!」
誰にともなく謝罪を繰り返す。こんな姿を優しかった父と母が見たとしたら何と言うだろうか? 悲しんでくれるだろうか? あるいは、この男の非常識な行為に憤ってくれるだろうか? 助けて、くれるのだろうか?
「なにがやめてだ、バカが。さっさと漏らしやがれ」
「あふっ!」
とどめの一撃だった。ずちゅ、と、指を根元まで入れられて亮子は呻いた。と、同時にぷしゃあああ、と破裂するような音が辺りに響く。自分の意志に反して体が感じ、いやらしい雫が辺りに飛び散ってしまう。こうして亮子は今日も、絶頂を迎えさせられてしまった。
「あ、あ……ああぁ……あ、ぁ……」
気持ちいい。その感覚が亮子の心をチクチクと傷つける。こんなに嫌なはずなのに、おかしいよと思う。何かが間違っている。自分は狂ってしまっているのかもしれないと、疑いを持ってしまう。
「あ、あああっ?」
休む暇など与えられはしない。亮子の小さな体は男の手によって簡単に持ち上げられ、足や腕を掴まれて逆さま……言うなれば噴水のように扱われてしまう。やがて、艶やかな桜の花びらの中に、亮子の秘所から飛び散った雫が交じっていく。雫の一粒一粒はきらきらと光り、綺麗にすら見える。
「や、やああっ! もう、離して……」
「ふん。この淫乱女が」
い、淫乱じゃないよ。お兄ちゃんのせいで、体が勝手にこんなふうになっちゃったんだよ。こんな惨めな、傷物の体にさせられちゃったんだよ。と、そんなことを訴えようものなら、圧倒的な力で首を絞められたり頬をつねられたり平手打ちされたり、酷い時は顔を踏み付けられたりする。だから何も言えない。
「う、うう。……ふ、服……。脱がさないで……。か、返して」
「お前に服なんかいらねえんだよ」
亮子の哀願に対し、寝言を抜かすなと、男は言いきった。いつの間にか、一枚残らず脱がされてしまっていた服。せめてそれだけはと思うけれど、拒否される。
「そんな……」
「前にも言っただろ? 本当は、家ん中でも裸にひん剥いて、鎖で繋いでおきたいくらいだ。服なんかお情けで着せてやってるんだから、それだけでもありがたく思え」
「そんな……」
もはや兄と妹の会話ではない。事実、この男は両親が不在の時には決まって亮子の服を剥ぎ取りにかかり、一日中裸で過ごさせたり、このような悪戯をしているのだった。時には首輪をつけさせたり、四つん這いにさせたり、尻を思いきり叩いたりと、完全に愛玩動物として扱っている。
「今日もこれからたっぷり可愛がってやるからな」
「あ、ああっ! あああっ!」
亮子は思う。……私は、違う。同年代の、他の娘達はこんな事、されていない。されるわけがない。私達はおかしい。狂っている。禍々しい現実がはっきりとわかる。どうしてこんな目に遭わなければいけないの? どうしてこんな事が許されているの? なぜ? 亮子の声に出せない問いかけは続く。
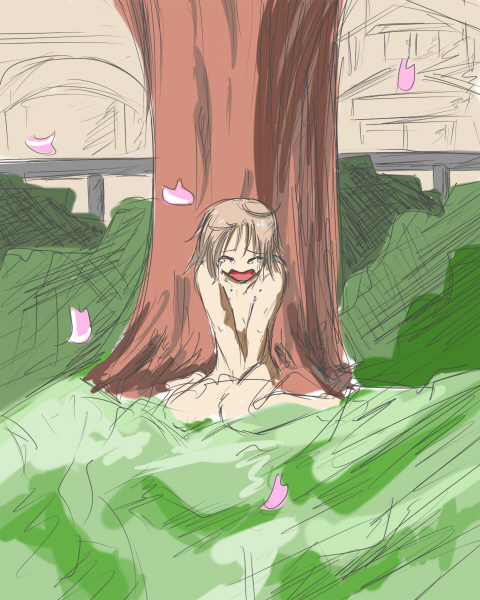
「立て」
男の手が伸び、桜の木の下でうずくまっている亮子を立たせにかかる。亮子のささやか過ぎる望みは涙と共に流れ落ちていく。ああ、また犯される。せめて……それならばせめて、乱暴にはしないでと言いたい。なのに言葉が出てこない。出せたとしても、余計乱暴に扱われるに違いない。そうして両腕で木にしがみつくよう促され、亮子はその通りにする。
「あああっ! いやああああっ! あああああああっ! きゃああああっ!」
めりめりと男の巨大な男性器が亮子の秘所を引き裂いていく。亮子は心の中で、父と母の名を叫び続けていた。
(もう、嫌だよおっ! こんなのっ! お父さん! お母さん!)
思い浮かぶのは、決して来ることのない、大好きだった人達の名。
「あ、あ、あん……あ、ん……んんんんっ!!」
ぱんぱんぱんぱんと、野生動物が交尾をしているかのような音が響いている。亮子は無意識のうちに甘ったるい声が出てしまっていることに気付いて、慌てて声を押し殺そうとするけれど、誤魔化すことなどできはしない。
「へっ。嫌だ嫌だ言いながらAV女優みてーなアヘ声出しやがって!」
「う、う……。うぅぅ……。ふ、ぅ……あ、ふ……」
違う、とは言えなかった。男は亮子の髪を無造作に掴んで引っ張っている。亮子は顔をのけぞらせながら喘いだ。歯を食いしばろうとするけれど、力が抜けてしまっていて、口がだらし無く空いていく。
「あ……」
ずびゅ、ずびゅ、と滲むように入ってくる感触。男が膣内に射精したのだ。
「う、う……」
流れ落ちる涙が幾筋にも別れていく。亮子の心は絶望感に満たされていく。
「ふう。これで一発目だ」
男は満足そうに溜息をついている。亮子の膣内から肉棒が抜けていくけれど、まだ始まったばかりだ。今度は尻の穴にでも宛てがわれていくのだろうと亮子が思っていたら、案の定、男の一物の先端にある亀頭が亮子の柔らかな尻の割れ目へとねじ込まれていく。
(お父さん……っ。お母さん……っ。助けて……っ。もう……もう、嫌なの……)
華奢な体を引き裂くように、ずぶずぶと肉棒が埋没していく。裂けそうなくらい小さな穴だろうと、男は容赦しない。
「あ、がっ! 許して……。もう……許し、て……」
ずんずんと前後に揺さぶられていく。亮子は白目を剥き譫言を呟きながら、猛烈な圧迫感に翻弄されていく。
(私……。おもちゃじゃない、のに……)
道具扱いされている悲しさに、亮子はただ俯く。
まだまだ凌辱の時は終わらない。亮子のアヌスを散々に犯して男が満足して……それでようやく束の間の休息が訪れる。ほんの僅かな休息の時が。
「なにマグロみてーになってんだよ。もっと鳴け。喚け」
「う、うう……ひゃいぃ……。あ、あん、あん……。ひいっ!」
言われるがままにしても、逆効果。ばちんと尻に手形がつきそうなくらい強く叩かれる。
「わざとらしいんだよバカが!」
「ひやああぁぁ! やめて! やめてぇぇ……痛いぃっ! た、叩かないでぇぇぇ」
「うるせえっ! ケツの穴で感じてる淫乱が! ぐだぐだぬかしてねーでアホみてーにイクイクいっちゃう気持ちいいとか言ってろ!」
「う、ぐ……。あぅぅ……。い、いっちゃいます……。い、いく……気持ちいい……です。ぐす……」
またしても男の一物がアヌスに入っていく。その度に、先に膣内へ出されていた精液が逆流し、糸を引いてたれていくのがわかる。きっとすぐにアヌスも、精液に満たされた状態になることだろう。
(助けて……助けて……。誰か……助けて……。もうやだあぁぁ……)
やがてまた、新たな射精が始まっていく。それと同時に亮子も達してしまい、全身をびくびくと小刻みに震えさせている。全裸の亮子を慰めるかのように、桜の花びらが散っていく。
「あ、あ、あ、あ、あ……っ」
大きな木にしがみつきながら、亮子は脱力してずるずると沈み込んでいく。男は一人で何か呟いている。仕上げに、今度は口の中をぐちょぐちょにかき混ぜてやるかな、と。新たな仕打ちに亮子は嗚咽を漏らす。
「ひっく、ひっく……」
「立て。おら、咥えろ! おめーの好きなち○ぽだぞ! しっかりしゃぶれ!」
「もごぉぉっ! むごっ! んぅぅぅぅっ!」
ただひたすらに、ぐちゅぐちゅと、哀れな少女を犯し尽くす音が、夜の闇に響いていった。